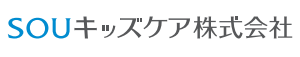コラム

- 2021.05.29
- コラム
認可外保育施設の設備・運営の基準とは?補助金についても解説

働き方の多様化や助成活躍の推進により、企業や病院内に保育施設が設置される事例が増えています。これらの業態は、「認可外保育施設」と呼ばれます。
認可外保育施設は、かつて国の認可を受けられない保育施設と見なされていましたが、今は違います。企業や病院の福利厚生を目的に設置されている「企業主導型保育施設」や「院内保育所」の中には、国から補助金を受けることで認可保育所よりも保育料が安かったり、独自の特色を打ち出しているところがあります。
この記事では、認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を説明するとともに、認可外保育施設のなかでも補助金が出る企業主導型保育所や院内保育所について詳しく解説します。
認可外保育施設とは?
保育施設は、「認可保育所等」と「認可外保育施設」の2つに大別されます。認可外保育施設は、認可保育所等以外の保育施設であり、児童福祉法に基づく都道府県知事などの認可を受けていない保育施設のことです。
「無認可保育園」とも呼ばれ、地方単独保育施設の「認証保育所」や、企業が従業員のために設置する「企業主導型保育施設」も認可外保育施設に含まれます。保育料やサービス内容を自由に設定できるため、認可基準を満たしていても、あえて独自の教育方法のために認可外にしている施設も存在します。
施設数の推移
厚生労働省の「平成30年度 認可外保育施設の現況取りまとめ」によると、平成31年3月31日時点の認可外保育施設数は12,027か所です。
全体の届出数は、前年の9,666カ所に比べ2,361か所増加しました。その要因は、「事業所内保育施設(ここでは認可外のみを指す)」で1,616か所、「認可外の居宅訪問型保育事業」で1,273か所(うち個人が1,243か所)増加しており、減少分よりも大きくなっていることが挙げられます。
また、都道府県は認可外保育施設の保育内容や環境を確認するため、原則年1回の立入調査を実施しています。立入対象の対象施設数は8,777か所とされており、実施されたのは6,433か所でした。
認可外保育施設の種類

認可外保育施設は開設や運営の自由度が高いため、認可保育所では対応できない規模や場所、時間外や日曜祝日、24時間の運営など、多くの形態が存在します。ここではその種類を紹介します。
企業主導型保育所
「企業主導型保育所」は、平成28年度から始まった新しい事業形態です。
企業で働く従業員の子どもを預かる保育施設であり、企業単独での設置(単独設置型)はもちろん、同じ地域にある複数の企業と一緒につくることもできます(共同設置型)。単独・共同設置型のどちらも、自社運営と外部委託が選択できます。
保育所の柔軟な設置と運営を助成するのが目的のため、国から運営費と整備費の補助金が出るのが最大の特徴です。また、地域枠として定員の50%以下まで地域の子どもを受け入れられるので、定員すべてが従業員の子である必要はありません。
企業枠が定員割れしても、待機児童解消を目的に、一定の要件を満たせば地域枠50%を超えての受け入れも可能です(弾力措置)。
ちなみに、企業主導型保育所と同じように企業内に設置する「事業所内保育事業」は、地域型保育事業の1つです。市区町村の認可が必要なため、こちらは「認可保育所等」に区分されます。
参考:内閣府「1. 企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリット」
院内保育所
「院内保育所」は、病院内で働く医師や看護師などの子どもを預かる保育施設です。病院内や病院隣接場所に設けられており、早朝や夜間、24時間保育に対応しているところもあります。
規模の大きい病院は24時間体制のため、夜勤時など時間を問わず子どもを預けられれば、医療従事者は離職することなく働けます。勤務する病院が経営しているのも安心できるポイントです。
直営で運営している病院もありますが、外部の委託業者に任せているケースが多く見られます。企業主導型保育所と同様に、要件を満たせば子育て支援の一環として助成金を受け取れる場合もあるため、人手不足を解消する施策としても注目が集まっています。
参考:厚生労働省 第67回社会保障審議会医療部会「参考資料1-4 院内保育等の推進について(PDF:5,478KB)」
東京都福祉保健局「病院内保育所運営事業について」
ベビーホテル
「ベビーホテル」は託児所のことで、赤ちゃん向けホテルというわけではありません。以下、3つの中からいずれかを満たす施設を指します。
- 夜8時以降の保育
- 宿泊を伴う保育
- 利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上
定員は10~20人程度の規模が多く、24時間体制の施設もあります。ホテルや百貨店に設置されるような一時預かりも受け入れる施設から、保育園のように継続して預かる施設まで幅広く存在します。
お勉強(教育)のようなことはあまりせず、子どもを見たり遊んだりするような保育内容が一般的です。
一時預かり
「一時預かり」は、その名の通り利用児童がすべて一時預かりの施設です。その意味ではベビーホテルと定義が重複する場合もあります。
歯医者や美容院、スポーツクラブなどの商業施設に常設されていたり、イベント開催時に臨時で設置して、一定時間子どもを預かるような施設がイメージしやすい思います。
居宅訪問型保育施設
保育訪問型保育施設はベビーシッターのことで、乳幼児の居宅で保護者の代わりに保育する事業です。
認可と認可外に分かれており、認可外保育施設の基準としては原則として1対1、自宅で保育する特性を踏まえ、保育士または看護師以外の従事者は一定の研修受講を要件としています。
ベビーシッターと保護者のマッチングサイトも存在するため、安全かつ安心な保育が行われるように、厚生労働省がガイドラインで基準を定めています。
参考:厚生労働省「認可外の居宅訪問型保育事業者の基準等の現状等」
厚生労働省「ベビーシッターなどを利用する時の留意点」
その他
国ではなく自治体が基準を定めている保育所もあります。例えば、「認証保育所」は東京都独自の制度です。
認可保育所の設置基準は、土地の広さや0歳児枠の設定など大都市に合わせるのが難しいため、東京都は「東京都認証保育所事業実施要綱」を定めているのです。
認証保育所には、「A型(駅前基本型)」と「B型(小規模、家庭的保育所)」の2種類があり、どちらも都知事の認可は受けられます。ただ、国の定めた基準からは外れるため、分類は認可外保育施設となります。
東京都のほかにも、大阪市や札幌市など独自の基準を定める自治体は増加傾向にあります。
認可外保育施設の基準
認可保育所でなく認可外保育施設でも基準が定められています。厚生労働省「認可外保育施設指導監督基準」と、内閣府「認可外保育施設の質の確保・向上について」を参考に、認可外保育施設の基準について解説します。
国の配置基準と自治体の配置基準が異なるケースもありますので、地元自治体のHPを必ずチェックしてください。
人員配置基準
1日に保育する乳幼児の数が6人以上、開所時間が11時間以内の場合は以下の通りです。
| 子どもの年齢 | 子どもの人数 | 必要な保育士 |
|---|---|---|
| 0歳児 | 3人 | 1人以上 |
| 満1歳~3歳未満 | 6人 | 1人以上 |
| 満3歳~4歳未満 | 20人 | 1人以上 |
| 満4歳以上 | 30人 | 1人以上 |
ただし、11時間を超える場合は、保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上の配置が必要とされています。
また、全体の従業員数の基準としては、常勤職員(1日6時間以上月20日以上または120時間以上の勤務者)により算出します。時短勤務(パートやアルバイト)の職員を充てる場合は、総勤務時間数を常勤職員に換算してから計算します。
職員の資格基準
保育に従事する3分の1以上が、保育士または看護師(助産師・保健師含む)の資格が必要です。
これらの基準を満たしていれば、残りの従業員に保育士の資格がなくても問題はありません。
設備の構造や面積の基準

認可外保育施設の設備基準について解説します。
子ども1人に対する広さ
1日に保育する乳幼児が6人以上の場合は、子ども1人に対し1.65㎡の広さが必要です。5人以下の場合は、適切に保育を行える広さを確保します。
0歳児の保育スペース
0歳児を保育する場所は、幼児(満1歳~就学前)とは別の部屋であることが望ましいとされています。
部屋を別にできない場合は、区画を設けるなどして安全性を確保する必要があります。
調理室の設置基準
保育室以外に、調理室とトイレの設置が必要と基準で定められています。ただ、施設外で給食を調達していたり、家庭からお弁当を持参してもらう場合は設置する必要はありません。
調理室を作らなくても、食品の加熱や保存、配膳に必要な調理設備(冷蔵庫、電子レンジほか)は必要です。調理室や食品を扱うエリアに乳幼児が立ち入らないよう、区画を設ける必要があります。
トイレの設備基準
トイレは他の部屋と区画を設け、かつ安全に使用できるように衛生面に配慮しなくてはなりません。
幼児20人に対し1か所以上のトイレを配置し、専用の手洗い設備を設ける必要があります。
保育室の環境の基準
保育室は採光と換気を確保しなくてはなりません。
また乳幼児用ベッドを使用する際は、1つのベッドに2人以上の乳幼児を寝かせてはいけないという基準があります。
非常災害対策の基準
消火用具、非常口など非常災害に必要な設備を設け、具体的な非常災害対策計画を作成しなくてはなりません。
非常口は災害時、2方向避難が可能となるように設けます。避難消火などの訓練は、最低でも毎月1回は必要です。
2階以上のテナント利用する場合の基準
保育室は原則として1階に設けるよう定められています。ただし、防災上必要な措置を講じれば、2階以上にも保育室を設置することができます。
2階に保育室を設ける場合
2階に保育室を設置する際は、以下の基準を満たす必要があります。
保育室を2階に設ける建物には、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
なお、保育室を2階に設ける建物が次のイ及びロをいずれも満たさない場合においては、第3に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。
イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。
(い) ①屋内階段 ②屋外階段 (ろ) ①建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段②待避上有効なバルコニー③建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備④屋外階段
つまり、乳幼児の転落事故を防止する設備が必要であり、耐火建築物であり、屋内階段や屋外階段もしくは、屋内特別避難階段、バルコニー、準耐火構造の傾斜路などが必要ということです。
3階・または4階以上に設ける場合
3階・または4階以上に保育室を設置する際は、以下の「イ」~「ト」までの基準をすべて満たす必要があります。
イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられていること。【3階】
(い) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する屋内特別避難階段②屋外階段 (ろ) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備③屋外階段 【4階】
(い) ①建築基準法施行令第 123 条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段②建築基準法施行令第 123 条第2項に規定する構造の屋外避難階段 (ろ) ①建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路③建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段 ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第 112 条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
- 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合
- 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合
ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
ホ 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
ヘ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
ト 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
これを簡潔にまとめると以下です。スプリンクラーや自動消火装置などの設備がないときは、耐火構造の床や壁にする必要があり、時にはダンパーが必要。さらに壁や天井は不燃材料で仕上げをしている、転落防止設備や警報や通報設備、防炎処理された建具などが必要となります。
そして、3階の場合には耐火建築物である必要があり、避難階段や屋内階段、屋内階段、耐火構造の傾斜路などを設置しなくてはならず、これらへの保育室からの歩行距離がいずれも30m以内でなくてはならないです。
そして4階の場合には、屋内避難階段、屋外避難階段、耐火構造の傾斜路が必要ということなのです。
ここまで認可外保育施設の基準について解説してきましたが、企業主導型保育所は別の基準が設けられているので注意が必要です。
企業主導型保育所の基準
企業主導型保育事業は、より質の高い保育が求められます。認可保育所と同程度の補助金が受けられるのもあり、認可外保育施設以上の配置基準が設けられています。
以下の項目ごとに内容をチェックしてみましょう。
| 企業主導型保育事業 | 認可外保育施設 | |
|---|---|---|
| 職員数 | 保育所(定員20人以上)の配置基準に対して追加で1名以上必要 ※最低2人配置 | 0歳児3人に対し1名以上 |
| 1~2歳児6人に対し1名以上 | ||
| 3~4歳児20人に対し1名以上 | ||
| 4~5歳児30人に対し1人以上 | ||
| ※最低2名配置(ただし子どもが1人のときは1人可) | ||
| 資格 | 全体の2分の1以上が保育士 | 1日に保育する乳幼児6人以上の施設の場合、全体の3分の1以上が保育士 |
| ※保健師、看護師、准看護師のみなし特例は1人まで | ※看護師、准看護師、助産師でも可 | |
| ※保育士以外には研修実施 | ※研修の義務はなし | |
| 面積 | 0~1歳児1人に対し 乳児室1.65㎡/人、ほふく室 3.3㎡人 | 子ども1人あたり 保育室1.65㎡ |
| 2歳児以上1人に対し保育室または遊戯室1.98㎡ | ※0歳児は他年齢幼児の保育室と別区画 |
職員配置数と職員資格
子どもの数に対する保育従事者数と、資格者の割合について解説します。
職員配置数は認可保育所とほぼ同じ
内閣府の企業主導型保育事業等によると、認可保育所と企業主導型保育所の保育者従事者数はほぼ同じです。
定員20名以上の子どもに対する保育従事者の数は、認可外保育所と同じ表を元に人数を算出し、合計人数に1人追加した数(小数点以下四捨五入)です。
また、乳幼児が1人しかない場合も、最低2人以上の保育従事者が必要です。
職員資格は全体の半分必要
また、企業主導型保育所では、全従業員のうち半分以上が保育士である必要があります。
保育の資格がない従業員は、地方自治体が実施する「子育て支援員研修」や、公募団体が実施する研修を受けなければなりません。
設備等の基準
企業主導型保育所の設備等の基準は、厚生労働省が定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について」と「認可外保育施設指導監督基準」を遵守しなくてはなりません。
子ども1人に対する広さ
また、企業主導型保育事業の子ども1人に対する面積は、以下のように定められています。
- 0~1歳児1人に対し、乳児室1.65㎡/人、ほふく室 3.3㎡人
- 2歳児以上1人に対し、保育室または遊戯室1.98㎡
運営が始まると、認可保育所と同様に行政の監査が入ります。基準割れや違反が見つかると、場合によっては助成取り消しになる可能性もあるのです。
保育施設向けの設置基準は、施行後の状況や法整備によって変化します。順次対応していくには、専門的な知識が必要です。
スクルドアンドカンパニーは、企業主導型保育所・院内保育の開園から運営までフルサポートします。設置基準や面倒な申請手続きに関するご相談にも無料でお答えします。ぜひご相談ください。
認可外保育施設の助成金の基準

基本的に認可外保育施設には助成金は出ません。しかし、すでにご説明した通り、企業主導型保育事業は認可施設並みの助成金を受け取れます。事業計画策定の前段階で、助成金の種類や加算要件の知識を深めておきましょう。
2020年6月現在、企業主導型保育事業の助成金は以下の4つです。
- 運営費
- 整備費
- 施設利用給付費
- 利用者負担額減免臨時給付費
1.運営費助成金の例
運営費は地域区分、定員区分、年齢区分、開所時間区分、保育士比率区分の5つを基準額をベースにして助成金を算出します。
以下は、東京都特別区で定員20名の助成例です。
乳児 256,400円×5人=1,282,000円(月額) 1歳児 171,640円×5人=858,200円(月額) 2歳児 171,640円×5人=858,200円(月額) 3歳児 108,980円×5人=544,900円(月額) 利用者負担相当額 △711,000円(月額) 月額合計 2,832,300円 年額合計 33,987,600円
2.整備費助成金の助成例
整備費助成金は保育所設置の工事費用にて適用される助成金です。人口密度区分と定員区分2つの基準額を基礎として基本単価を算出し、実際にかかった対象工事の費用に4分の3を乗じた額と比較し、低い方の額が助成されます。
補足として、測量費や外構工事、厨房設備や保育備品などは対象外です。また、改修工事の場合は整備費ではなく運営費に適用されます。
以下は利用定員20名以上、満2歳以上の幼児を入所させる場合の助成例です。
保育室又は遊戯室、屋外遊技場、調理室及び便所(幼児用便座)の設置
基本単価 定員20名(都市部) 83,600千円 地域交流・一時預かりスペース加算 2,730千円 病児保育スペース加算 21,700千円 設計料加算(基本単価の5%) 4,180千円 計 112,210千円 ※上記は基準額の上限であり、実際は対象工事の実支出額の3/4との比較によって助成額が決定されます。
引用:企業主導型保育事業ポータル「企業主導型 保育事業助成金」の概要及び支給額等(3)助成金(整備費)
3.施設利用給付費の助成例
企業主導型保育施設の無償化は、保育料を一度施設に払った後に、自治体に対し無償化の給付請求を行います。この無償化給付のことを「施設等利用費」といいます。
利用者負担相当額の年齢区分ごとに、無償化対象児童数を乗じて得た額の合計額を、基準額として算出します。
利用者負担相当額(1人あたり月額)
4歳以上児 23,100円 3歳児 26,600円 1、2歳児 37,000円 0歳児 37,100円
4.利用者負担額減免臨時給付費の助成例
新型コロナウイルスの影響で臨時休園した場合、利用者が保育サービスの提供を受けていないのに対し、利用料免除を行う際の臨時的な助成金です。
<計算式>
ア:週7開所施設
年齢区分ごとの利用者負担相当額×その月の上記に該当する欠席日数÷30日
イ:週7未開所施設
年齢区分ごとの利用者負担相当額×その月の上記に該当する欠席日数÷25日
ウ:週6未満開所施設
年齢区分ごとの利用者負担相当額×その月の上記に該当する欠席日数÷20日
引用:企業主導型保育事業ポータル「企業主導型 保育事業助成金」の概要及び支給額等(5)助成金(整備費)
まとめ
認可外保育施設は、長時間保育や夜間保育、休日保育など、柔軟な保育サービスを提供できます。また、認可外保育施設の運営をお考えの方は、助成金などが得られる企業主導型保育事業がおすすめです。
ただ、企業主導型保育事業を開設するには、さまざまな基準をクリアする必要があります。スクルドアンドカンパニーは企業内保育所の開設、受託運営実績が豊富であり、認可外保育園を含む40園以上の運営実績があります。
経営者様のビジョンや思いを明確にし、新規開設の申請代行や行政の監査対応までフルサポートいたします。企業主導型保育所、院内保育の申請サポートはもちろん、保育士の採用や園児の集客、園運営に必要なノウハウも提供いたします。
ぜひ一度、スクルドアンドカンパニーにお問い合わせください。