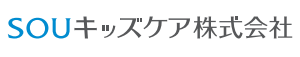コラム

- 2021.06.24
- コラム
企業内保育所を立ち上げるには?開設までの流れと設置要件

現在では企業内に保育所を設置する動きが活発になっています。
しかし、いざ企業内保育所を設置しようと思っても、保育所の種類により設置要件や開設手続きは異なるなど、簡単に設置できるというものでもありません。企業内保育所立ち上げまでの流れを、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。
企業は社内の保育ニーズを把握するとともに、物件や設備などのハード面と、申請手続きや人材確保といったソフト面を平行して準備していかなければなりません。
この記事では、企業内保育所の設置を検討されている企業に向けて、企業内保育所を立ち上げるまでの流れを解説します。
立ち上げるならどれ?企業内保育所の種類
企業内保育所とは、企業が自社で働く従業員のために、社内や近隣に設置する保育所のことです。企業内に保育所を設置することにより、従業員は離職せずに産休や育休が取得しやすくなり、企業は計画的な人員の確保・配置が実現できます。
企業内保育所は大きく分けて「認可保育所」「認可外保育所」の2つに分けられます。それぞれ設置要件や開設手続き、助成金の有無など異なります。大まかな特徴は以下の通りです。
| 種類 | 申請先 | 従うべき基準 | 助成金 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 認可保育所 | 地方自治体 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準ほか | あり | 設置基準は厳しいが、助成金を受け取れるので安定的に運営していける。 |
| 認可外保育所 | 地方自治体 | 認可外保育施設指導監督基準ほか | なし ※自治体によっては助成を受けられる場合もある | 基本的に助成金などのサポートはないが、企業のスタイルに合った保育を展開できる。 |
それでは、企業内保育所の種類について詳しく見ていきましょう。
1.認可保育所
認可保育所とは、国の定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認められた保育所のことです。
ゆとりをもった保育を実践するため、子どもの年齢や人数に合わせて保育士の人数が厳密に定められており、調理室や静養室などの設置義務もあります。保育所の設備や運営は、「建築基準法」「バリアフリー法」「児童福祉法」などに適合させる必要があります。
これらの基準を満たさなくてはならず、立ち上げや運営のハードルも高めとなります。ただ、認可されれば国や自治体から助成金が支給されるので、安定した状態で事業を継続できるといえます。
2.認可外保育所
認可外保育所とは、認可保育所以外の保育施設のことであり「無認可保育園」とも呼ばれています。長時間保育や宿泊できるベビーホテル、託児所やベビーシッターなども認可外保育に含まれます。
認可保育所に比べると、立ち上げの際に遵守すべき設置基準・運営基準・職員配置基準は比較的ゆるいです。そのため、延長保育や24時間保育など、保護者の保育ニーズや企業の就業スタイルに合わせて運営できます。近年はオリジナリティのある保育を提供するため、あえて認可を受けずに運営する施設も見受けられます。
認可外保育所に対し、国や自治体からの助成金などは基本的にありません。ただ、自治体が独自に設けた保育料・保育環境・保育時間などの基準を満たすことで、運営経費の助成が受けられる「認証保育園(東京都独自基準)」や「横浜保育室(横浜市独自基準)」などは存在します。
企業主導型保育所
認可外保育所のなかには「企業主導型保育所」も含まれます。企業主導型保育所とは、内閣府の助成制度を活用して立ち上げた保育所のことです。認可外保育所でありながら、一定の条件を満たすことで、認可保育園並みの助成を受けられます。
政府は平成28年度から令和3年まで計4回、定員11万人の受け皿確保を目標に企業主導型保育所の募集を行いました。
内閣府の「企業主導型保育事業点検・評価委員会(第10回)資料2」によると、令和3年3月末までに、10.5万人分の保育施設が開所しています。現在は受付終了しています。
企業内保育所を立ち上げるまでの6ステップ
ここからは、企業内保育所を立ち上げるまでの流れを解説していきます。
1.保育所の設置検討と社内のニーズの把握

企業内保育所を設置する背景は、企業によって異なります。例えば、社員の産休・育休サポート、新規採用の魅力付け、社員満足度向上、休日・夜間人材の確保などのように様々な理由が考えられます。
保育事業への参入を視野に、企業内保育所からスタートしてノウハウを蓄積していくケースもあります。
まずは社内の保育ニーズを把握するため、従業員に対しアンケートやヒアリングを実施しましょう。このタイミングで保育所設置のメリットを伝えておくことも大切です。
従業員に伝えるべき企業内保育所のメリット
- 働き方に応じて柔軟な保育サービスを提供できる
- 夜間や土日祝日、短時間保育にも対応できる
- 地域の子どもを受け入れる選択肢もあるので地域貢献にもなる
従業員に対するアンケートやヒアリングでわかること
- 子どもの人数
- 子どもの年齢層
- 預ける時間帯(夜間、土日祝日、短時間、延長の有無など)
- 保育所がどこにあると便利か
- 産休、育休のスケジュール
これらの確認をきちんと行うことで、保育所設置の目的が明確になります。
2.設置方法を検討
企業内保育の設置形態は、大まかに「単独設置型」と「共同設置型」の2つに分けられます。
単独設置型は保育所の設置を1社のみで行い、自社の従業員の子どもだけを受け入れます。そのなかでも単独設置・地域開放型は、地域に児童も受け入れます。
共同企業型は複数の企業が保育所に関わる形態です。自社が設置した保育所に対し複数企業の子どもを受け入れる「代表企業型」と、設置段階から複数企業が費用負担して設置する「フラット型」があります。
| 設置形態 | 特徴 |
|---|---|
| 単独設置型 | 自社が自社の従業員の子どもを対象に、保育所を立ち上げる。 |
| 単独設置・地域開放型 | 自社が自社の従業員の子どもと、地域の児童を対象に保育所を立ち上げる。 |
| 共同設置型(代表企業型) | 自社が立ち上げた保育所を、近隣の他社やグループ企業が共同で利用する。 |
| 共同設置型(フラット型) | 自社を含めた複数企業が保育園の設置に関り、運営のために別組織を立ち上げる場合もある。 |
認可外保育所の場合、園児や従業員の確保まですべて自社で担わなければならないため、共同設置を選択することで初期投資や運用負担を軽減できます。
3.運営方法(直営・委託)を検討
企業内保育所は、自社で運営する「自主運営方式(直営)」と、外部の業者に運営を委託する「外部委託方式(委託)」を選択できます。
どちらを選んだとしても、申請手続きの流れや助成金額に差異はありません。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
自社運営方式のメリット・デメリット
自社運営方式のメリットはコストです。保育所運営に関わるすべての事項を自社でまかなうため、コンサル料や委託料はかかりません。
デメリットは開設・運営負担です。初めて企業内保育所を立ち上げる場合、どういった物件が保育所に適しているのか、保育士の募集や教育の流れなど、開設に関わるノウハウがないとスムーズに進行するのは難しいでしょう。
開設後も、園児募集や年間カリキュラムの作成や立入調査対応、行政報告など、専門的な業務が多く発生します。
もう一つ考えておきたいのが風評被害です。故意過失を問わず、万一事故が発生した場合、悪いイメージが企業に付きまとう可能性があります。
外部委託方式のメリット・デメリット
外部委託方式のメリットは、開設・運用負担の軽減とリスク分散です。多くの委託業者は過去にいくつもの保育所を立ち上げた実績があり、物件の選定から人材採用、教育などのノウハウを持っています。
地域枠を設ける認可外保育所の場合、園児募集のための集客戦略は必須です。それも委託企業がノウハウを持っているので、募集が集まらないというリスクを避けられます。
また、万一事故や事件が起きたとしても、企業名が先行することはないので、風評被害を避けられます。
デメリットはコストが高くなる点です。ただ、ノウハウがない状態で自社運営方式を選択するよりも、外部委託方式を選んだ方が安定的かつ継続的に運営していける可能性は高いでしょう。
このように比較するとわかりますが、企業内保育所の設置や運営はプロに任せることをおすすめします。
スクルドアンドカンパニーは、企業内保育所の企画開発から運営までフルサポートします。申請業務から人材採用、スタッフマネジメントまですべてお任せください。開設準備、保育スタッフ派遣な部分的な保育サービスも承ります。
4.設置基準を確認して設置場所を決める

企業内保育所の設置基準は、開設する保育所の種類により異なります。児童一人当たりの面積や建物の構造、必要な設備を確認し、適切な物件を選定しましょう。
企業内保育所を設置する場所は、企業が所有している土地・建物でなくとも問題ありません。従業員に関係する場所であれば開設可能です。
設置場所の基準
| 事業所内の敷地 | 企業が所有する土地・建物に新設する。もしくは既存物件を保育施設に沿った仕様に変更する。 |
| 事業所の近接地 | 事業所付近に土地・建物を確保する。共同設置型を採用する場合は、企業の中間点。 |
| 従業員の通勤経路 | 通勤に利用する駅ビル、駅に近接する物件など。 |
| 従業員の居住地の近接地 | 従業員がまとまって住む社宅や団地に近接する場所。 |
近隣住民や関係機関との調整の上、物件を確定し、その後レイアウトや運用概要(開設時間、費用、保育カリキュラム、保育指導計画や年間行事計画の作成)の大枠を定めていきます。
認可外保育施設の面積の基準や従業員の人数など、詳しい設置基準については以下で紹介しています。
5.助成金申請
多くの場合企業内保育所を作るのは認可外保育所となりますが、認可外保育所に助成金はありませんので、申請業務は発生しません。
ただ、認可外保育所のひとつである企業主導型保育事業には助成金制度がありましたが、現在は募集は終了しています。
6.保育所の準備と利用者の募集
企業内保育所を立ち上げる物件が決まったら、開設に向けて具体的な準備を進めていきます。
施設の整備
備品や遊具や家具など、保育所に必要な設備を整えます。万一の事故に備えるため、設備や備品の配置を見直したり、事故発生時のマニュアルを整備します。
このタイミングで、賠償責任保険や傷害損害保険への加入手続きを済ませましょう。
保育所を開設する際に必要となる備品については、以下で紹介しているので参考にしてください。
保育士募集・教育
保育士の採用は、なるべく早い段階から余裕を持って開始します。
保育士に特化した求人媒体や人材紹介を駆使して、キーパーソンとなる園長や保育士資格保有者にアプローチします。
また、保育サービスの質を向上させるため、自治体や関係団体の開催する研修への参加の機会を設けることも大切です。
利用者負担額の決定
利用者の負担額を決定します。認可外保育所の場合、保育料に制限はありません。
従業員の保育料を低めに設定することで、福利厚生や人材確保の一環として活用できます。
利用者の募集
認可外保育所の場合、自社もしくは委託業者が園児を募集しなければなりません。募集要項を作成し、定期的に説明会を開催しましょう。
保育所の整備が整い、備品配置など済んだ状態であれば、見学会も実施します。その後、申し込みのあった保護者と面談を行い、入所手続きを進めます。
まとめ
企業内保育所を立ち上げるなら、全体の流れを把握してから着手するとスムーズです。
ただ実際に立ち上げる場合には、設備基準や人員配置条件など満たさなければならない項目が多く、開設までの手続きも複雑です。
運営開始後は、認可外保育所であっても認可同様に行政の立入調査が入ります。企業内保育所の運営に関わる基準は毎年更新されるため、最新の情報をチェックしながら日々の保育所運営に反映させていかなければなりません。
自治体に提出する運営状況報告書に虚偽が見つかれば罰金が課されることもあり、保育施設に基準割れや違反があれば、最悪業務停止命令が発令されることもあります。こういったリスクを回避するためにも、実績豊富な委託会社に立ち上げサポートを依頼しましょう。
スクルドアンドカンパニーは、企業内保育所の立ち上げや受託運営実績が豊富です。直営認可保育所を含む40園以上を運営しており、保育士の採用や園児の集客、園運営に必要なノウハウを提供できます。