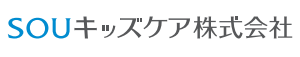コラム

- 2021.08.19
- コラム
保育園の安全対策とは?事例とデータをマニュアルに活用しよう

保育園における重大事故の件数は、毎年過去最多を更新しています。子どもの成長過程で一切ケガをしないという状況は考えにくいですが、保育園は死亡や重篤な事故を防ぐためにも安全対策を講じなければなりません。
過去に発生した事例に学び、起こりうる事故や事件を予測して対策を取るのが大事です。そのデータを元に安全対策マニュアルを作成し、従業員への周知、共有を図るのがよいでしょう。
この記事では、園内外で事故の発生リスクが高い場所を説明するとともに、損害賠償責任の事例についても解説します。
保育園に安全対策が必要な理由

保育園における子どもの重大事故は、残念ながら毎年発生しています。そうした中で、死亡や重篤な事故とならないよう、予防と事故後の安全対策が重要です。
2020年に保育園等で発生した重大事故は2015件
事故の報告を義務付けた2015年以降、重大事故件数は増え続けており、毎年過去最多を更新しています。
政府の公表データによると、2020年に全国の保育園等で発生した事故で0~4歳児5人が死亡。内訳は食べ物による窒息事故が3人、乳幼児突然死症候群(SIDS)が1人、原因不明が1人、となっています。事故が発生した場所は、認定こども園2人、認可保育所1人、認可外保育施設2人です。
死亡者数は前年より1人減少しているものの、重大事故の報告件数は2015件で、前年より271件増加しています。
重大事故にはヒヤリハットが隠れている
ヒヤリハットとは、ヒヤリとしたり、ハッとしたりする瞬間のことで、労働災害の安全対策によく用いられる「ハインリッヒの法則」と一緒に使われます。
1件の重大事故の背後には、重大事故に至らなかった29件の軽微な事故が隠れており、さらにその背後には事故寸前だった300件の異常、いわゆるヒヤリハットが隠れているというものです。
保育園生活の中でヒヤリハットへつながる事象を把握、収集し、即座に安全対策を講じることで、重大な事故やトラブルを防ぐことができます。
保育園での事故の情報を蓄積
保育園での事故の情報は内閣府によって蓄積されているので、こういったデータを見て対策を行わなくてはなりません。
内閣府は、「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」に基づき、保育園などで「死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等」の重大事故が発生した場合、原則として事故当日、遅くとも事故発生翌日に保育戦が所在する市町村の保育担当課を通じ、県への報告を義務化しています。
また、報告のあった事故に関連する情報を「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」にまとめ、年間の事故報告件数とそれらの要因や年齢、発生場所を「教育・保育施設等における事故報告集計」としてホームページ上に公開しています。
【場所別】保育園の安全対策
子どもの命を守るために、保育園の安全対策は必須です。
ここでは、厚生労働省の「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に、場所別の安全対策について解説します。
お散歩・公園など

- 天気や気温をチェックし、リスクがある場合は室内遊びに変更する。
- 交通量の少ない道、時間帯を選ぶ。
- 出発前・散歩先・到着時に人数確認する。
- 出発前に道路の歩き方、渡り方、公園など現地での遊び方を指導する。
- 避難散歩車の使用時は、つかまって立たせ、手や身体を乗り出さないようにする。
- 散歩中に動物・自動車・バイク・自転車・看板等に触らないよう指導する。
- 園外から枝・棒切れ・BB弾などを保育園に持ち込まないように指導する。
水遊び・プール
- 十分な監視体制の確保ができなければ、プール活動中止も選択肢とする。
- 時間的余裕をもってプール活動を実施する。
- 監視者は監視に専念し、監視エリア全域をくまなく監視する。
- 規則的に目線を動かしながら監視する。
- 動かない子どもや不自然な動きをしている子どもを見つける。
食事
誤嚥・窒息
- 子どもの意志に合ったタイミングで与える。
- 一回で多くの量を詰めすぎず、子どもの口に合った量で与える。
- 食べ物を飲み込んだことを確認し、口の中に残っていないか注意する。
- 汁物などの水分を適切に与える。
- 食事の提供中に驚かせない。
- 食事中に眠くなっていないか注意する。
- 正しく座っているか注意する。
- 過去に誤嚥や窒息の起きた食材(白玉風だんご、ミニトマト等)は使用しない。
アレルギー
- 材料等の置き場所と調理する場所を切り分ける。
- 食物アレルギーの子どもの食事を調理する担当者を明確にする。
- 材料の容器、食物アレルギーの子どもに使う食器など、色や形を明確に変える。
- 除去食、代替食は普通食と形や見た目が明らかに違うものにする。
- 食事内容を記載した配膳カードを作成し、2重3重のチェック体制をとる。
食中毒
- テーブルは、清潔な台布巾で水拭きをして、衛生的な配膳・下膳を心掛ける。
- スプーン、コップ等の食器は共用しない。
- 食後には、テーブル、イス、床等の食べこぼしを清掃する。
- 調乳室は清潔に保ち、調乳時には清潔なエプロン等を着用する。
- 哺乳瓶、乳首等の調乳器具は、適切に消毒して衛生的に保管する。
- 乳児用調製粉乳は、使用開始日を記入し、衛生的に保管する。
- 乳児用調製粉乳は70℃以上のお湯を使い、2時間以内に使用しなければ廃棄する
トイレ
- 水はねにより床が滑らないか確認する。
- 個室内の安全が確認できるようにする。
- 手洗いの流しの周りに陶器・ガラス物等割れる物は置かない。
- おむつ交換台に子どもを乗せている時は、絶対に目を離さない。
園庭
- 固定遊具や砂場、乗り物、植物や飼育物等の扱い方を職員間で情報共有しておく。
- 常に人数把握し、遊び場の変更や保育士がその場を離れるときは声を掛け合う。
- 不審者の侵入や子どもの飛び出しに注意し、出入り口を施錠し管理する。
- 毎朝危険なものないか、犬猫の糞など不衛生なものがないか、点検を怠らない。
- 転倒時の安全と、陽射しを避けるため、常時帽子を着用させる。
- 園庭倉庫は子どもが中に入らないよう十分注意して管理する。
- 植物や樹木に突起物や害虫がいないか点検、確認する。
- 植物や樹木、花は毒性のないものを選ぶ。
- 倉庫や用具入れの戸は子どもが自由に開閉できないようにする。
- フェンスネットがはずれて引っかかる危険のないよう、整備点検する。
- 門扉の鍵は子どもが簡単に開けられないものにする。
【年齢別】保育園の安全対策
子ども行動、生活パターンを元に、年齢別の安全対策について解説します。
0歳児
- 医学的な理由でうつぶせ寝が必要な場合を除き、顔が見える仰向けに寝かせる。
- 口の中に異物、ミルクや食べたもの等の嘔吐物がないか確認する。
- ベビーベッド使用中は必ず柵を上げ、柵には物を掛けない
- 寝ている子どもの上に、物が落ちてこないよう安全を確認する。
- ミルクを飲ませた後は、ゲップさせてから寝かせる。
- 誤飲防止のためやわらかすぎる布団、ぬいぐるみ等は使用しない。
- ベビーベッドの柵とマットレス、敷き布団の間に隙間のないことを確認する。
- よだれかけ、ふとんカバーのヒモ、ベッドまわりのコード等を置かない。
- 定期的に呼吸、体位、睡眠状態を点検し、呼吸停止等の異常を早期発見に努める。
- 窒息のリスクがある場合は記録し、施設・事務所内で共有する。
1歳児
- ハサミやカッターなどの刃物は、使用後すぐに片付ける。
- 鼻や耳に小物を入れて遊ばせない、小さな玩具は撤去する。
- ベランダや玄関など段差のある所に一人で行かせない。
- イスの上に立ち上がったり、イスをおもちゃにして遊ばせない。
- 子どもに合った靴を履いているか、身体に合った衣類を着用しているか確認する。
- 玩具を持ったまま、カバン等を身体にかけたまま固定遊具で遊ばせない。
- トイレ用の洗剤や、消毒液は子どもの手の届かない所で管理する。
2・3歳児
- 室内では走らせず、人数や遊び方を工夫して衝突を防ぐ。
- おもちゃの取り合いなどの機会をとらえて、安全な遊び方を指導する。
- 子どもが引き出しやドアを開け閉めして遊んでいないか注意する。
- 遊具の上でふざけたり、危険な遊びをさせないようにする。
- 固定遊具の近くで遊ぶ際、勢いあまって衝突することがないよう注意する。
- ビニール袋やヒモなどは、子どもの手の届かない所で管理する。
4歳児以上
- テーブルやイスに立ち上がったり、揺らしたり逆さにしないよう指導する。
- お箸など先が尖ったものを持って歩き回ることがないよう注意する。
- トイレや手洗い場、室内、廊下、テラスでは走らせないよう指導する。
- フェンスや門など危険な高い場所に上らないように指導する。
- 石や砂を投げてはいけないことを指導する。
- 滑り台や鉄棒、登り棒など保育士が近くにいないときは使わないように指導する。
- 縄跳びの安全な遊び方やロープの正しい使い方を指導する。
保育園で安全対策を計画し実施するには、精度の高いマニュアルが必要です。マニュアルの内容はもちろん、従業員に周知されるよう運用していくことが事故防止につながります。
スクルドアンドカンパニーは、40園以上の運営実績を元に、園ごとのマニュアル、安全対策におけるオペレーションなど提案可能です。
保育園の安全対策に関する損害賠償請求事例
保育園で事故の過失性が問われるのは、事故の発生を予測できながら、安全対策といった結果を回避するための行為が不足した場合です。
ここでは、過去に起きた3つの事故と、損害賠償額などの事例について解説します。
午睡中の乳幼児死亡事故
認可外保育園に預けられた1歳の子どもが、うつぶせ寝の体位で急死した事故です。
従業員が子どもを早く寝付かせるためうつぶせにし、頭部から足元にかけて四つ折りにした大人用の毛布をかけました。さらに、背中から腰の辺りに巻きタオルケットを横向きに2枚乗せ、40分以上も放置したのです。
裁判所は乳児の死因はSIDSによるものではなく、うつぶせ寝による窒息死であると判断。保育従事者の過失を認定し、施設経営者らの共同不法行為責任を認めました。損害賠償請求は約6,500万円、判決認容額(支払い額)は約5,800万円です。
ビニールプールでの溺死
認可外保育園のベランダに設置されたビニールプールで、3歳の子どもが溺死した事故です。担当の保育士が保護者対応のため子どもから目を離し、その間に溺死してしまいました。
裁判所は一般的な幼児の水の事故に関し「水深が数センチ程度であっても発生することが珍しくない」と指摘し、「他の保育士に女児の動静を確認するよう依頼した上で、その場を離れる義務があったのに怠った」として、賠償責任を認めました。損害賠償請求は約6,700万円、判決認容額は約3,400万円です。
遊具に首を挟まれ窒息する死亡事故
認可保育園で3歳の子どもが遊具のうんていに首を挟まれ、事故発生から10分後に保育士が発見。低酸素脳症で9カ月後した事故です。
うんていは別の保育園の特注品で、遊具メーカーなどの業界団体が設定した安全基準を満たしていませんでした。園側は遊具の基準や危険性を認識しておらず、裁判所は「遊具の危険性を放置し、組織として過失がある」として、賠償責任を認めました。
損害賠償請求は運営法人と園長、保育士に対し約5,500万円、判決認容額は運営法人に対し約3,100万円です。
保育園の安全対策には従業員の教育が重要
事故防止には、従業員の安全対策に対する意識、行動が求められます。保育園を運営する中で、定期的な研修を実施し、救急対応や事故発生時の適切な処置方法を学ぶ機会を設けましょう。
緊急時の役割分担(心肺蘇生・応急措置・病院付き添い・保護者連絡)を決めておき、たとえ小さな事故であっても、再発防止に向け協議する場を設けます。安全対策マニュアルの熟知はもちろん、緊急時の体制を整えることが大切です。
まとめ
子どもの行動は大人の予想をはるかに超え、思いがけないことの連続です。だからこそ、大きな事故につながる可能性のある事例を細かく記録し、原因の分析、予防策を従業員間で共有しなければなりません。
スクルドアンドカンパニーは直営を含めた40園以上の運営実績があり、運営委託により国のガイドラインに沿った安全対策を実施できます。精度の高い安全対策マニュアルやチェックリスト、従業員教育プログラムの提案も可能です。