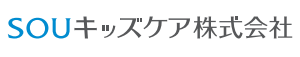コラム

- 2021.09.21
- コラム
保育園の運営のために知っておくべき法律とは?
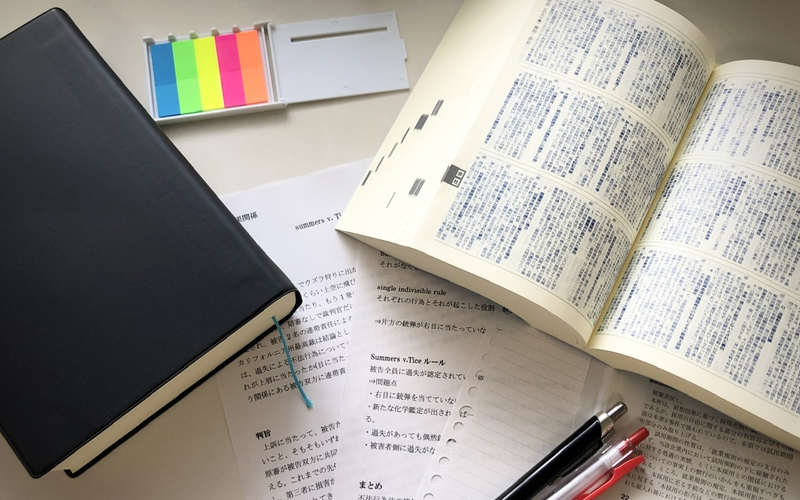
保育園を設立して運営していくには、さまざまな法律が関係してきます。運営方針に係る児童福祉法や建築基準法、消防法など、保育園を運営する経営者はこれらの法律を周知するとともに遵守しなければなりません。
万一法律に違反した場合、知らなかったでは済まされずある日突然法的措置を取られてしまう可能性もあるのです。この記事では、保育園に関連する法律と関連する項目をピックアップして紹介します。保育園の開設を考えている方はぜひ参考にしてください。
法律の定義
法律には階層関係があり、厳密には法律に含まれないものなど、様々なものがあります。ここでは保育園の運営に関係する、法律・政令・省令・基準・条例までの法体系を「法律」として紹介します。
| 種類 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 法律 | 国で制定された法律や規則 | 児童福祉法など |
| 政令 | 児童福祉法施行令など | |
| 省令 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準など | |
| 基準 | 法令ではないものの、最低限満たすべき義務的ルール | 認可外保育施設指導監督基準、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準など。 |
| 条例 | 地方自治体で制定された法律や規則 | 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例など |
保育園の運営方針に関する法律

保育園の運営方針にかかわる法律を紹介します。これらの法律は重要ですので、必ず抑えておきましょう。
児童福祉法
児童福祉法には、児童の福祉を担う公的機関やその組織、事業に関する基本的な原則が定められています。児童福祉法のなかでも保育園の運営にかかわる省令と項目は、以下の通りです。
第45条第1項「児童福祉施設最低基準」
保育園が一定の基準を保持し、児童の福祉を保証できるよう最低基準についてまとめてある箇所です。保育園を設置して運営していくには、この児童福祉施設最低基準にある設備と運営の基準に適合させなければなりません。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 設備の設置 |
|
| 職員の配置 |
|
| 保育時間 |
|
| 保育内容 |
|
参考:児童福祉法
第46条「行政庁の監督」と第58条「認可の取消し」
自治体が保育園を立入検査し、最低基準を維持できていないときは、事業の停止や認可を取り消せることについてまとめてある箇所です。
保育園の設置されている自治体は、適切な保育と保育環境が確保されているか確認し、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令などを行わなければなりません。基準に達していなければ保育園の設置者に改善を勧告、その後児童福祉に有害であると判断した場合は、改善を命じることができます。
さらに、児童福祉に著しく有害であると認めた場合、児童福祉審議会(第8条第2項)に規定する都道府県の意見を聞き、事業の停止や認可を取り消すことができます。
認可外保育施設指導監督基準
認可外保育施設指導監督基準には、認可外保育園が守るべき設備と運営の最低基準と、自治体の改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令等を行う際の手順について定められています。
参考URL:厚生労働省「認可外保育施設指導監督基準」
認可外保育園に該当する施設は企業主導型保育所、院内保育所、ベビーホテル、一時預かり、居宅訪問型保育施設などで、それぞれの設備・運営の基準については以下の記事で詳しく紹介しています。
保育園の開設・運営に関する法律
保育園の開設・運営に関する法律を紹介します。
建築基準法
建築基準法には、建築物の敷地・設備・構造・用途の最低基準が定められいます。保育園は社会福祉施設に該当し、病院・ホテル・共同住宅等と同じ区分です。
保育園に関連するのは、土地建物の構造や建物内部の壁紙・天井の防火素材、建物外部の廊下や階段の防火素材であり、園児と従業員を事故や火災から守るために以下のような内容が定められています。
| 法令 | 該当箇所 | 内容 |
|---|---|---|
| 建築基準法 | 第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物) | 保育施設を3階以上の階に設ける場合は耐火建築物、2階の部分の保育施設の用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 |
| 建築基準法施行令 | 第23条(階段、踊場等の寸法) | 居室の床面積の合計が200㎡を超える場合、幅120cm以上、蹴上20cm 以下、踏面24cm以上上記以外の場合、幅75cm以上、蹴上22cm以下、踏面21cm以上。 |
| 第119条(廊下の幅) | 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階両側に居室がある場合幅1.6m以上、その他の場合幅1.2m以上。 | |
| 第120条(居室から直通階段に至る歩行距離) | 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合、居室から直通階段に至る歩行距離を50m以下としなければならない。主要構造部が上記以外の場合は30m以下。 | |
| 第121条(2つ以上の直通階段を設ける場合) | 保育所の用途に供する階で、その階における保育所の用途に供する居室の床面積の合計が50㎡を超える場合には、2つ以上の直通階段を設けなければならない。※主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合は100㎡。 | |
| 第126条の2(排煙設備の設置) | 保育所の用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超える場合には排煙設備を設けなくてはならない。ただし、床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されている部分等(第126条の2第1項第1号等)及び平成12 年建設省告示第1436号に定める部分には設置不要。 | |
| 第126条の4(非常用の照明装置の設置) | 保育所の用途に供する特殊建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる通路等には非常用の照明装置を設けなくてはならない。ただし、窓その他の開口部を有する居室及びこれに類する建築物の部分※(以下「居室等」という。)で①又は②に該当するものには設置不要。① 避難階の居室等で当該居室等から屋外への出口までの歩行距離が30m以下。② 避難階の直下階又は直上階の居室等で当該居室等から避難階における屋外への出口等までの歩行距離が20m以下。 | |
| 第128条の4・第128条の5(内装制限関係) | 耐火建築物の場合、保育所等の用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上の場合に、当該用途に供する居室及び当該居室から地上に通ずる主たる通路の内装制限を受ける。 |
参考:建築基準法
消防法
消防法には、消防機関の活動や権限、消防設備等の設置や義務、規制などが定められています。保育園に関連するのは、消防用設備に関する技術基準、救急業務、消防設備に関する検査等です。
注意点として、事務所ビルに保育園が入居すると、その建物は消防法で「複合用途防火対象物(2つ以上の異なる用途がある防火対象物)」になる場合があります。設置基準がより厳しくなるため、事前確認が必要です。
建物の階数や面積に応じて定められている消防用設備は以下の通りです。
| 消防用設備等の種類 | 消防用設備等の設置基準 | 事務所(15 項) | 保育所 (6 項ハ) | 複合用途 (16 項イ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消火設備 | 消火器具 | 一般 | 300㎡以上 | 150㎡以上 | 各部分の用途による(150 ㎡以上) |
| 地階・無窓階・3 階以上 | 50㎡以上 | 50㎡以上 | 各部分の用途による(50 ㎡以上) | ||
| 屋内消火栓 | 一般 | 2,000㎡以上 | 1,400㎡以上 | 各部分の用途による(1,400 ㎡以上) | |
| 地階・無窓階・3 階以上 | 400㎡以上 | 300㎡以上 | 各部分の用途による(300 ㎡以上) | ||
| スプリンクラー | 一般 | ‐ | 6,000㎡以上 | 3,000㎡以上 | |
| 4~10 階 | ‐ | 1,500㎡以上 | 1,500 ㎡以上 | ||
| 11 階以上 | 全部 | 全部 | 全部 | ||
| 階数が 11 階以上の防火対象物 | ‐ | 全部 | 全部 | ||
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 一般 | 1,000㎡以上 | 300㎡以上 | 300 ㎡以上 |
| 地階・無窓階・3 階以上 | 300㎡以上 | 300㎡以上 | 300 ㎡以上 | ||
| 11 階以上 | 全部 | 全部 | 全部 | ||
| 漏電火災警報器 | 1,000㎡以上 | 300㎡以上 | 延べ500㎡以上かつ6項300㎡以上 | ||
| 消防機関への通報装置 | 1,000㎡以上 | 500㎡以上 | 各部分の用途による(500 ㎡以上) | ||
| 非常警報器具・設備 | 収容人数 | ‐ | 300人以上 | 500人以上 | |
| 階数 | 地下3、地上11以上 | 地下3、地上11以上 | 地下3、地上11以上 | ||
| 避難設備 | 避難器具 | 設置条件 | 150人以上 | 20人以上 | 10人以上 |
| 必要個数 | 600人に1つ | 200人に1つ | 200人に1つ | ||
| 誘導灯・誘導標識 | 地階、無窓階11階以上の部分 | すべての階 | すべての階 | ||
参考:消防法
食品衛生法

食品衛生法とは、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
保育園の食事提供は自園調理が原則でしたが、平成10年に調理業務の委託、平成22年より満3歳以上に給食の外部搬入方式が可能となりました。直近の動きとして、令和3年6月1日よりHACCPに沿った営業の許可・届出制度がスタートしています。
自園調理の保育園は「施設の設置者又は管理者による新たな制度に基づく届出」もしくは「調理受託事業者による許可の取得」をしなければなりません。調理業務を外部事業者に委託し給食を提供する保育園は、受託事業者が飲食店営業の許可を取得する必要があります。
参考:食品衛生法
保育園の給食に関連する項目は多岐にわたるため、ここでは割愛します。保育園の給食については、厚生労働省「保育所における食事の提供ガイドライン」を参考にしてください。
事業所内保育園に関する法律
事業所内保育に関連する法律を紹介します。事業所内に保育園を作る場合にはチェックしておきましょう。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準には、「家庭的保育事業」「小規模保育事業」「居宅訪問型保育事業」「事業所内保育事業」の設置や運営に関する基準が定められています。
事業所内保育事業は地方自治体(所在地市町村)の認可が必要なため、各地方自治体が定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」を遵守する必要があります。
自治体独自の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」
国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」をそのまま運用している自治体もありますが、保育の質を担保するため、より厳しい設置基準を制定している自治体もあります。
ここでは、横須賀市と東京都中央区の事例を紹介します。
横須賀市
横須賀市は、職員の設置基準を国より厳しく定めています。
| 事業 | 国基準 | 横須賀市基準条例 |
|---|---|---|
| 小規模型事業所内保育事業 | 保育従事者のうち半数以上は保育士とする。 | 保育従事者のうち4分の3以上は保育士とする。 |
参考URL:横須賀市「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」
中央区(東京都)
中央区は、事業所内保育事業(地域枠を設定する保育所のみ適用)に一部上乗せして基準を設けています。
| 事業 | 国基準 | 中央区基準条例 |
|---|---|---|
| 小規模型事業内保育所※地域枠を設定する保育所のみ適用 | 保育従事者のうち半数以上は保育士とする。 | 保育従事者数のうち6割以上を保育士とする。 |
参考URL:中央区「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」
まとめ
保育園を開業するには、物件の選定やレイアウト、職員配置にいたるまで、法律の知識が欠かせません。
複数の法律が関わってくるため、保育園の運営の実績がないと開業までスムーズに進行するのは難しいでしょう。開業できたとしても、運営基準に達していなければ業務停止の可能性もあります。
スクルドアンドカンパニーは、保育事業専門の弁護士や社会保険労務士、会計士・税理士、建築設計事務所と密接な連携を図っているため、保育園のあらゆる問題を解決できます。
40園以上の運営実績があり、開業から運営委託までフルサポート可能です。基準に則った開業サポートや運営カリキュラムをご提案しますので、お気軽にご相談ください。