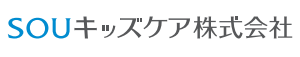コラム

- 2021.11.24
- コラム
保育園の認可に必要な条件とは?認可と認可外のそれぞれの基準を説明

新たに保育園を開設するときには、自治体の認可を受けなければなりません。
保育園には認可保育園と認可外保育園がありますが、国は認可保育園と認可外保育園それぞれで要綱に基づいた設置基準・運営基準を定めています。そして、保育園の形態を問わず、自治体への認可申請や届け出が必要です。
この記事では、認可保育園と認可外保育園が認可されるにはどのような条件があるのか、設置基準と合わせて紹介します。
認可保育園の認可に必要な条件や基準

認可保育園は認可保育施設に分類され、認可保育園の実施主体は自治体であり、開業後は自治体と連携・相互協力して保育事業を実施するため、児童福祉法第35条の規定に基づいて市長村長による認可が必要です。
認可保育施設の種類には、以下のようなものがあります。
| 認可保育施設の種類 | 定員 | 対象児童 | |
|---|---|---|---|
| 認可保育園(公立・私立) | 20名以上 | 0歳~就学前 | |
| 地域型保育施設 | 小規模保育施設 | 6~19名以下 | 0歳~2歳 |
| 事業所内保育施設 | |||
| 居宅訪問型保育 | 保育士:子ども(1:1) | ||
| 家庭的保育施設 | 1人以上5人まで | ||
事業者は安全で質の高い保育を確保するため、各自治体の定める条件や厳しい基準を満たさなければなりません。
また、認可保育園の設置は原則公募制で、設置枠数や申請者要件等も細かく定められています。これらをクリアし、自治体との協議を経て認可された保育園のみ認可保育園として開業できるのです。
ここでは、厚生労働省の「保育所の設置認可等について」を元に、認可保育園の認可に必要なポイントを紹介します。以下は抜粋した内容ですので、必ず自治体の要綱などをご確認ください。
事業者(経営者)の条件
保育所を設置する事業者は、社会福祉法人、学校法人、株式会社、NPO法人等の法人格を有し、保育所を経営するために必要な経済的基礎がある者とされています(居宅訪問型保育事業を除く)。
事業者は、年間運営費の12分の1以上に相当する資金を普通預金、当座預金等に有している必要があり、法人全体が3年以上連続して損失を計上していないことが求められます。また、以下の項目に該当していると審査は通過できません。
- 法人税、消費税、地方消費税、都道府県民税、市町村民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税及びその他の税を滞納している。
- 社会保険料を滞納している。
- 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない。
- 申請日前6ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している。
さらに、自治体や地域と連携するため、以下の項目を満たす必要があります。
- 設置する認可保育園専用の口座を設ける。
- 法人格に関わらず「社会福祉法人会計基準」に基づいて資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表等による会計処理を行う。
- 設置する認可保育園に適用する経理規程を整備する。
- 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 社会福祉法人以外の法人の場合は運営委員会を設置する。
- 業務上取得した個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に取り扱う。
- 地域交流や行事への招待など、近隣住民との良好な関係づくりに努める。
設置場所
保育施設として活用できる土地・建物には、以下のような要件が定められています(居宅訪問型保育を除く)。
- 定員に対する建築面積及び延床面積を確保できる土地・建物である。
- 建築基準法42条に定義される道路に接している土地・建物である。
- 隣地・道路との境界が確定している土地である。
- 二方向の避難経路確保など、安全性が担保されている土地・建物である。
- 新耐震基準により建築された建物である。
参考URL:港区「保育施設として活用できる土地・建物を募集します」
また、事業者が不動産を賃貸して保育所を設置する場合は、貸与を受けている不動産について地上権又は賃借権を設定し登記する必要があります。
ただ、建物の賃貸借契約期間が運営開始日から10年以上、もしくは土地の賃貸借契約期間が運営開始日から20年以上なら、地上権や賃借権は不要です。
参考URL:厚生労働省「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」
保育者の資格と数

事業者(経営者)には保育士など特別な資格は求められませんが、保育現場にいる保育者には、資格と適正な人数配置が求められます。ただ、設置する認可保育園の施設設備や職員を活用し、通常保育以外の延長保育などのサービスを実施する場合はこの限りではありません。
事前にサービス内容を自治体に申請し、職員配置や施設設備等において事業が継続的に実施できる体制を整えます。
施設長の要件
施設長の要件には、次のようなものがあります。全てを満たす必要はありませんが、複数の要件を満たさなければなりません。
- 保育士資格がある。
- 認可保育園または認定こども園で常勤職員として2年以上の実務経験がある。
- 認可保育園または認定こども園に、幹部役職員として10年以上従事した経験がある。
- 児童福祉事業に2年以上従事した経験がある。
- 「保育所長等研修」または「社会福祉施設長資格認定講習課程」を修了している。
- 社会福祉主事の資格がある。
保育士の要件
保育士の数や資格は、国が配置基準を定めています。
| 認可保育施設の種類 | 保育士と子どもの割合 | 職員の資格 | |
|---|---|---|---|
| 認可保育園(公立・私立) | 0歳児は子ども3人につき保育士1人以上、1~2歳児は子ども6人につき保育士1人1以上、3歳児は20人、4~5歳児は30人に保育士1人以上を配置。 | 保育士 | |
| 地域型保育施設 | 小規模保育施設 | A型とB型は認可保育園の配置基準+1名(1/2が以上が保育士)、C型は0~2歳児3人に対し1人。 | A型は保育士、B型は1/2が以上が保育士、C型は家庭的保育者。 |
| 事業所内保育施設 | 定員20名以上は認可保育園と同じ、19名以下は小規模保育事業のA型、B型と同じ。 | ||
| 居宅訪問型保育 | 0~2歳児(1:1) | 必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長村長が認める者 | |
| 家庭的保育施設 | 0~2歳児(1:1)家庭的保育補助者を置く場合(5:2) | 家庭的保育者(+家庭的保育補助者) | |
表中の家庭的保育者は、市町村長が行う研修を修了した保育士、または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者のことです。
自治体によっては、さらに厳しい要件を上乗せして設けている場合もあります。
設備及び面積
認可保育園の設備と面積に関しては、都市計画法、建築基準法、消防法、その他自治体の条例や規則、通知について遵守する必要があります。
乳児室(0歳児室)及びほふく室(1歳児室)は保育室(2歳児以上室)とは別の区画とし、天井までの壁等で仕切られた独立の室とすることが望ましいとされています。乳児室とほふく室を一緒にする場合は、安全の確保に留意します。
保育室などは1階に設けることが望ましいとされていますが、2階以上に設ける場合は、屋外階段や屋外特別避難階段などによる2方向避難経路を確保しなければなりません。
面積の基準は乳児室1.65㎡以上/人、ほふく室は3.3㎡以上/人、保育室は1.98㎡以上/人です。
指導監査
児童福祉法第46条に基づき、自治体は保育園に対して指導監査を実施します。チェック項目は児童福祉法施行令第38条に基づき、年1回以上の実地検査が義務付けられています。
事業者は自治体が行う保育内容等に関する指導助言を積極的に受け入れ、その指導助言に対する改善を図らなければなりません。
参考URL:児童福祉法
補助金の認可
自治体に補助金の申請をして認可を受けられれば、補助金を受給できます。
認可保育園の補助金には、保育園を建設・改修する「整備費」と、人件費や事業費等にかかる「運営費」に関わるものがあります。整備費の補助金は、以下の補助制度に定められています。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| 「保育所等整備交付金交付要綱(令和3年7月6日改正)」 | 新たに認可保育園を建設または増設するときに交付される補助制度。 |
| 「保育所等改修費等支援事業の実施について」 | 賃貸物件で認可保育園を改修するときに交付される補助制度。 |
| 「都市部における保育所等への賃借料等支援事業」 | 地価の高い都市部において、賃借料の一部を補助する制度。 |
運営費の補助金は、内閣府が毎年発表する「令和3年度公定価格単価表」に基づいて算出され、毎月必要書類を自治体に提出することで受け取ることができます。
認可保育園の補助金については、以下のサイトで詳しく紹介しています。
認可外保育園の認可に必要な条件や基準
認可保育園の次には、認可外保育施設の認可について解説します。
認可外保育園には、以下のような種類があります。
- 家庭保育室
- 認可外保育園
- 企業主導型保育施設
- 認証保育所
- 横浜保育室
- ベビーホテル
- 病院内保育所
- 一時預かり施設
- ベビーシッター
認可外保育施設は、あくまで認可保育園の基準に満たない施設であり、児童福祉法では施設の届出や定期報告、情報の公表、市町村への通知等が明確に規定されています。
ここでは、厚生労働省「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」を元に、認可外保育園の認可に必要なポイントを紹介します。
事業者(経営者)の条件
認可外保育園は種類によって法人しか認められない場合、個人でも開設できる場合があります。例えば、企業主導型保育施設・認証保育所・横浜保育室などは、法人でなければならないとされています。
また、認可外保育施設を開設した場合は、児童福祉法第59条の2第1項により、事業開始の日から1月以内に市長村長への届け出が義務付けられています。そして、施設の運営状況を毎年自治体に報告しなければなりません(児童福祉法第59条の2の5)。
参考URL:「児童福祉法」
保育者の資格と数
認可外保育園は、保育者の3分の1以上が保育士又は看護師資格が必要です。
主たる保育時間が11時間を超えない場合は、0歳児は子ども3人につき保育士1人、1~2歳児は子ども6人につき保育士1人1、3歳児は20人、4~5歳児は30人に保育士1人とされています。
11時間を超えるときは、保育されている子どもが1人の場合を除いて、常時2人以上の保育者が必要です。
設備及び面積
認可外保育施設の設備及び面積は、子どもの人数によって基準が異なります。
ただ、最低基準である「認可外保育施設指導監督基準」においては、保育室の面積はおおむね乳幼児1人当たり1.65㎡以上と定められています。
立入調査
認可外保育施設のうち、届出対象施設については年1回以上立入調査を行うことを原則としています。
当日、自治体の職員が保育者に聞き取り調査を行い、軽微なものはその場で改善します。重大な問題(設備や配置基準の違反等)は後日文書で指摘され、おおむね1ヵ月以内に改善報告を提出しなければなりません。
参考URL:「認可外保育施設の確保・向上について(参考資料)」
補助金の申請手続き
認可外保育施設に国の補助金は交付されませんが、自治体によっては独自に補助制度を設けている場合もあります。
また、企業主導型保育事業のみ認可保育所並みの助成金を受け取ることができます。企業主導型保育事業の助成金は以下の4つです。
- 運営費
- 整備費
- 施設利用給付費
- 利用者負担額減免臨時給付費
認可外保育施設の認可基準や補助金については、以下でより詳しく解説しています。
まとめ
認可保育園は補助金が交付されますが、基準が厳しく開業までの道のりは困難です。
一方、認可外保育園には補助金がないものの、認可のハードルは低く、経営の自由度や開業のしやすさがあります。認可の要件や基準は保育園の形態によって異なるため、保育事業に参入するなら自社に合った形態を選ぶのがよいでしょう。
スクルドアンドカンパニーは、様々な認可外保育園の運営実績があります。物件選定や申請業務代行などの開業サポートも可能です。事業者の方に、最適な保育園を提案できますので、お気軽にご相談ください。