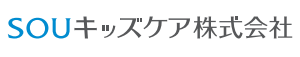コラム

- 2022.01.20
- コラム
小規模保育園の開業に必要なこととは?流れや設置要件や収支例などを解説

小規模保育園はその名の通り小規模の保育園のことであり、比較的短期間で開業できます。国や自治体から補助金も交付されることから、多くの人が取り組んでいる保育園です。
ただ、小規模保育園を開業するためには、物件の広さや設備など、様々な要件を満たさなければなりません。申請に必要な書類は多岐にわたり、手続きも複雑です。
そこでこの記事では、小規模保育園の開業を検討している経営者の方に向けて、開業までに必要なことや開業までの流れを紹介します。収支やスケジュールの事例も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
小規模保育園とは
小規模保育園とは、定員6〜19人以下、0〜2歳の子どもを対象としている保育施設のことです。小規模保育園は、定員20人以上の認可保育所と、定員5人以下の家庭的保育の中間に位置しており、その中でさらにA型・B型・C型の3種類に分かれています。
以下の表は、一般的な認可保育園と小規模保育園の要件を比較したものです。
| 種類 | 認可保育園 | 小規模保育園A型 | 小規模保育園B型 | 小規模保育園C型 |
| 定員 | 20名以上 | 6人以上19人以下 | 6人以上19人以下 | 6人以上10人以下 |
| 職員資格 | 全員保育士 | 全員保育士 | 1/2以上が保育士 | 家庭的保育者 |
| 職員数 | 0歳:子ども3人に職員1人 1~2歳:子ども6人に職員1人 |
認可保育園の配置基準+1人 | 認可保育園の配置基準+1人 | 0〜2歳:子ども3人に職員1人 (補助者を置く場合は5人に2人) |
| 保育室の面積 | 0歳~1歳…1人当たり3.30㎡ 2歳児…1人当たり1.98㎡ |
0歳~1歳…1人当たり3.30㎡ 2歳児…1人当たり1.98㎡ |
0歳~1歳…1人当たり3.30㎡ 2歳児…1人当たり1.98㎡ |
1人当たり3.30㎡ |
小規模保育園は、「子ども・子育て支援法」によって平成27年より自治体の認可事業となり、補助金が交付されるようになりました。
小規模保育園の特徴や運営のメリットについては、以下のページで詳しく紹介しています。
小規模保育園を開業する流れとは?

ここでは、厚生労働省「認可保育所等設置支援事業の実施について」を元に、企業が小規模保育園を開業する流れについて解説します。
以下は一例であり自治体によって異なる要件を設定しているため、開業する自治体の要件を確認しましょう。
1.物件をチェックする
小規模保育園は、自治体の認可事業であるため、いつでも誰もが小規模保育園を開業できるわけではありません。
各自治体が待機児童数や保育の質の確保、就業率の向上などを考慮して、翌年4月に必要となる小規模保育園の数を決めます。自治体によっては、形態(A型・B型・C型)や必要定員、特に誘致したいエリアなど細かく指定しているところもあります。
毎年4〜6月頃に自治体のホームページなどで事業者の募集が開始され、企業はそこに応募して初めてスタート地点に立ちます。
ただ、募集が出てから開業準備をしても間に合いません。募集の出そうな自治体を事前にリサーチして、適切な物件を探しておく必要があります。
2.募集要件の内容をチェックする
募集要項は自治体のホームページなどにアップされますが、自治体によって事業者に対する要件も変わってくるので注意が必要です。
例えば、待機児童が多く、小規模保育園を急ピッチで増やしたい自治体は、多くの企業に参入してもらうために要件を広げます。逆に、すでに保育園が飽和傾向にあり、保育の質を高めたい自治体は、より厳しい基準を設けます。
以下は、横浜市と船橋市の募集要件(令和4年4月開業予定)を比較したものです。
| 自治体名 | 横浜市 | 船橋市 |
|---|---|---|
| 募集形態 | 小規模保育園A型又はB型 | 小規模保育園A型 |
| 募集回数 | 年3回 | 年1回 |
| 事業者の要件 |
|
|
参考URL:
横浜市「令和4年4月開所 小規模保育事業(3次募集)」
船橋市「小規模保育事業A型を設置・運営する事業者を募集します※現在は募集終了」
横浜市は、改修費に係る補助金の交付を受けなければ、要件に当てはまる全法人が応募することができます。対して船橋市は、すでに保育事業に参入しており、認可保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業(A型)のいずれかを2年以上運営している事業者しか応募できません。
小規模保育園の開業を検討しているなら、どの地域であれば新規参入できるのか、事前に戦略を立てておく必要があります。
3.補助金制度をチェックする
補助金を申請するのは自治体の審査通過後になるのですが、開業資金を補助金でどの程度補填できるのか、抑えておく必要があります。
小規模保育園の補助金制度は、整備費と運営費の2本柱です。整備費は小規模保育園の開業に伴う増改築、改修、修繕工事などが対象です。運営費は、子どもの年齢や従業員数などの区分に従って毎月金額が決まります。
補助制度の内容は自治体によって異なり、待機児童解消や女性の就業率向上に積極的な自治体は、国の基準に上乗せしてさらに手厚い補助金制度を設けています。
以下は、国が公表している補助金の一例です。要件を満たせば確実に受け取ることができます。各自治体独自の補助金制度については、各自治体のホームページをチェックしてください。
| 補助制度 | 概要 | 金額参考(一部抜粋) |
| 保育所等整備交付金 | 保育園の新設・修理・改造・整備にかかる経費や防音壁の整備、防犯対策の強化にかかる費用の一部を補助するもの。 |
|
| 保育所等改修費等支援事業 | 賃貸物件を活用して保育所等を開業する際など、設備運営基準を満たすために必要な改修費等の一部を補助する。 | 1施設あたり:15,000千円 (緊急対策参加自治体は20,000千円、待機児童対策協議会に参加する等一定の要件を満たす自治体は23,000千円) |
| 保育所等におけるICT化推進等事業 | 保育の周辺業務や補助業務に係るICT等を活用した業務システムの導入を支援するもの。 | 1施設当たり:1,000千円 |
| 地域型保育給付(運営費等補助金) | 保育所の定員規模や入所児童の年齢区分等によって運営費を補助するもの。 | 子ども1人あたり:150〜300千円/月が目安(公定価格+加算分) ※開業場所、子どもの人数、職員数などにより上下するため、おおよその数値です。 |
| 保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援 | 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、保育所等の消毒に必要となる経費を補助するもの。 | 1施設当たり:500千円以内 |
参考URL:厚生労働省「令和4年度 保育関係予算概算要求の概要」
補助金で賄えない範囲は融資も検討しましょう。厳しい審査を通過した小規模保育園の社会的信頼度は高く、融資が受けやすくなる可能性があります。
例えば、独立行政法人福祉医療機構は、小規模保育園を開業する事業者に対して、通常融資率80%のところ、90%まで引き上げて貸付を実施しています。
また、賃貸での開業には無担保貸付制度を用意しており、設置・整備資金の無担保貸付限度額を通常300万円から3,000万円に引き上げる優遇融資を実施しています。
参考URL:独立行政法人福祉医療機構「福祉貸付事業 融資のご案内」
4.収支計画を立てる
小規模保育園の設立費と、開業後の運営費について収支計画を立てましょう。
設立費用のイメージ
以下の表は企業主導型保育事業の設立費の参考値ですが、小規模保育事業に近い設置要件のため、設立費用の参考にしてください。内閣府「企業主導型保育事業立ち上げ事例のご紹介」より、19名以下の施設を抜粋しました。
開業場所にもよりますが、2,600〜5,000万円となっています。
| エリア | 開業場所 | 園児定員数 | 設立費用 | 費用補足 |
| 東京都杉並区 | 本社建物内(2階) | 10人 | 2,600万円 | 開園準備費、外階段整備費を含む |
| 東京都武蔵野市 | 学校敷地内、合宿所改修 | 8人 | 約4,775万円 | 建物支出、製氷機や食洗機などの備品支出、人件費等を含む |
| 東京都国分寺市 | 事業所内設置(1階) | 12人 | 約4,500万円 | – |
| 和歌山県和歌山市 | 近隣ビル(2階) | 18人 | 約2,800万円 | – |
運営費用のイメージ
開業後の運営費は、厚生労働省「令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果<速報値>【修正版】」のデータを参考にできます。
以下の表は、小規模保育園(A型・B型・C型)の収支状況です。
| 科目 | 小規模保育園A型 339事業所 |
小規模保育園B型 185事業所 |
小規模保育園C型 30事業所 |
||||
| 金額(千円) | 構成比率 | 金額(千円) | 構成比率 | 金額(千円) | 構成比率 | ||
| 収益 | 保育事業収益 | 45,696 | – | 37,710 | – | 27,140 | – |
| 児童福祉事業収益 | 49 | – | 11 | – | 421 | – | |
| その他収益 | 441 | – | 175 | – | 51 | – | |
| 借入金利息補助金収入 | 1 | – | 0 | – | 4 | – | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | – | 15 | – | 0 | – | |
| 特別増減による収益 | 1,075 | – | 629 | – | 966 | – | |
| 費用 | 人件費 | 29,626 | 64.8% | 24,359 | 64.6% | 17,233 | 62.5% |
| 事業費 | 3,562 | 7.8% | 3,552 | 9.4% | 2,117 | 7.7% | |
| 事務費 | 6,279 | 13.7% | 4,859 | 12.9% | 2,930 | 10.6% | |
| その他の費用 | 791 | 1.7% | 609 | 1.6% | 251 | 0.9% | |
| 支払利息 | 51 | 0.1% | 23 | 0.1% | 13 | 0.0% | |
| 法人本部帰属経費 | 722 | 1.6% | 662 | 1.8% | 0 | 0.0% | |
| 収益計 | 45,746 | 100.0% | 37,736 | 100.0% | 27,565 | 100.0% | |
| 費用計 | 41,031 | 89.7% | 34,064 | 90.3% | 22,545 | 81.8% | |
| 収支差 | 4,716 | 10.3% | 3,672 | 9.7% | 5,021 | 18.2% | |
令和元年の小規模保育園の収支差率はA型10.3%、B型9.7%、C型18.2%でした。私立保育所(2,167施設)の収支差率は2.3%であることから、保育事業の中でも採算性が高いことがわかります。
5.開業までのスケジュールを立てる

開業までの大まかなスケジュールを立てます。
小規模保育園の設立は、準備を開始してから10〜11ヵ月ほどです。定員20名以上の認可保育園はおおよそ2〜3年かかるため、比較的短期間で開業できるといえます。
ただ、申請書類作成などのソフト面と、改修工事などのハード面を短期間で同時に進めるため大変です。
以下はスケジュールの一例です。自治体によって内容は異なります。
| 時期 | 自治体との協議 | ハード面の準備 |
|---|---|---|
| 5月~6月末日 | 協議申込書受付期間 |
|
| 7~8月 | 協議対象施設の選定・審査 |
|
| 10月 | 一次利用調整(選考)申込み開始 | |
| 1月 | 認可・確認申請書提出 | |
| 2月 | 一次利用調整(選考)結果通知 |
|
| 3月 | 事業認可・確認 | |
| 4月 | 事業開始 |
6.物件の選定と施設長の確保
応募受付(4〜8月)の段階で開業予定の物件情報と施設長の情報が必要になるため、物件を選定して施設長を確保します。
物件は建築基準法や都市計画法、消防法などを遵守している土地建物で、A型とB型は0歳〜1歳児1人当たり3.30㎡、2歳児1人当たり1.98㎡。C型は1人当たり3.30㎡の広さを確保しなければなりません。
また、施設長は次のうちいずれか1つを満たしている必要があります。
- 保育士資格を有し、認可保育所において常勤職員として2年以上の実務経験を有する者。
- 児童福祉事業に2年以上従事し、「保育所初任保育 所長研修会」または「社会福祉施設長資格認定講習課程」を修了した者。
- 社会福祉主事の資格を有し、かつ児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者。
自治体によってはさらに条件を上乗せしている場合もあります。
参考URL:東京都福祉保健局「保育所設置認可等事務取扱要綱」
7.応募書類・申請書類を準備する
開業予定地と施設長が決まったら、自治体に提出する書類を準備します。以下は必要書類の参考例です。
| 開業計画に関連する書類 |
|
| 事業者に関連する書類 |
|
| 物件に関連する書類 |
|
| 運営に関連する書類 |
|
8.内装工事を行う
無事審査を通過したら、内装工事に着手します。
翌2〜3月頃に自治体の検査があるため、検査に間に合うよう施設設備を完成させなければなりません。滞りなく検査を通すためにも、保育園の実績が多い施工会社を選びましょう。
整備費補助金は工事完了後に交付されるケースが多いため、資金は全くの持ち出しになる可能性があります。
内装デザインについては、以下のページで詳しく紹介しています。
また、保育園を開業するときに必要な備品については、以下のページで詳しく紹介しています。
9.教育カリキュラムの作成と保育士採用
小規模保育園では、教育カリキュラムの作成と保育士の採用が必要になります。
ちなみに、保育所経営は経費の6~7割を人件費が占めます。「マイナビ中途採⽤状況調査2020年版」によると、保育業界分野の1人当たりの求人広告費は83.9万円。厚生労働省「保育の現場・職業の魅力向上に関する報告書」によると、保育士の離職率は9%であり、定期的に採用コストを投下しなければなりません。
カリキュラムの作り方については、以下のページで詳しく説明しています。
最後に、入園を検討している保護者に対して見学会や説明会を開催し、入園希望者と面談します。小規模保育事業は認可事業のため、園児の募集と配置はすべて自治体が行ってくれます。このような準備を経て開業へ至ります。
まとめ
小規模保育園は採算性が高く、短期間で開業できる保育事業です。
国は令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備するとしています。また、内閣府「まち・ひと・しごと創生総合戦略」によると、女性の就業率は令和7年に82%まで増加すると予測されています。
保育サービスの需要は高いままであり、国や自治体の後押しがある今、開業するには良い時期であると言えるでしょう。
ただ、厳しい認可基準をクリアするには、自治体との交渉や申請書類作成など、開業に関するノウハウが必要です。
スクルドアンドカンパニーは100園の運営実績があります。保育園の運営に精通していますので、お気軽にお問い合わせください。