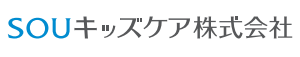コラム

- 2021.06.30
- コラム
企業主導型保育事業で実際にもらえる助成金とは?申請の流れも紹介

企業主導型保育事業は、その助成の手厚さから多くの事業者が申請をしました。
この記事では、助成金の対象項目となる運営費・設備費の内訳を説明するとともに、助成金を受け取るまでの流れについて詳しく解説します。
企業主導型保育事業の助成金とは?
企業主導型保育事業とは「企業が従業員の働き方に応じ、柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育所」や「地域の企業が共同で設置し運営する保育所」を設置する企業に対し、助成金を支給する制度です。
助成金の受給要件
助成金の対象となるのは、従業員の働き方に応じたサービスを提供する保育所であり、必要な基準を満たすことで助成金を受け取れます。
企業主導型保育事業の制度を活用して開設する保育所は、「認可外保育所」に分類されます。本来、認可外保育所は助成金を受給できないのですが、以下の要件を満たすことで助成対象になります。
- 子ども、子育て拠出金を負担している一般事業者である
- 平成28年4月以降に新たに保育所を設置する場合(平成28年以前に事業所内保育を実施しているあ売、新たに定員を増やしたり、空き要因を他企業向けに割り当てる場合も対象)
※令和3年度の募集はすでに終了しています。
助成対象の項目
助成対象となる項目は、「保育所を運営するときに必要な経費(運営費)」と「保育所設置に伴う工事費用(整備費)」の2種類です。運営費助成金は保育所の運営に関わる費用、整備費助成金は保育所の工事にかかる費用が対象です。
それぞれ基本単価(基本の助成金)に加え、該当する工事や事業に加算される「加算金(助成金の拡大)」があります。
以下では、運営費と整備費について解説します。
企業主導型保育事業の運営費に対する助成金
運営費の助成金の内訳

企業主導型保育事業の運営費の内訳は、「基本分」「加算分」の2つです。
基本分は毎月の運営状況に基づいて計算され、地域区分・定員区分・年齢区分・開所時間区分・保育士比率ごとに基準額が定められています。加算分には以下のような項目(一部抜粋)があります。
| 項目 | 内容 | 助成額目安 |
|---|---|---|
| 預かりサービス加算 | 一時預かりの実施 | 2,676,000~最大47,880,000円(1事業あたり年額/一般型) |
| 延長保育加算 | 開所時間を超えての延長保育を実施 | 276,000~最大4,536,000円(1事業当たり年額) |
| 夜間保育加算 | 夜間のお泊り保育を実施 | 13,080~47,890円(1人当たり月額) |
| 保育補助者雇上強化加算 | 職員配置基準に追加して子育て支援員を別途配置 | 2,333,000円(1事業当たり年額) |
| 賃借料加算 | 保育所が賃貸物件の場合 | 2390000~最大5794000円(1事業当たり年額) |
参考:内閣府「企業主導型保育事業補助金実施要綱 単価表(令和3年5月12日【改定予定版】) 3.01 MB」
これらの項目の内容を行うことで助成金を得ることができるのです。
運営費の助成金のイメージ

例えば、東京都特別区で定員20名(満2歳以上受け入れ、11時間開所、週7日未満)の保育所が企業主導型保育事業の制度を活用すると、地域差はあるものの、運営費に対する助成金は年間3,400万円前後となります。
目安としては、運営費に対する助成は子ども1人あたり月額15~30万円前後となります。月齢、年齢が低いほど助成額は高くなります。以下は、中小企業が企業主導型保育所を開設した場合の事例となります。
| 東京都心(中小企業) | 地方都市(大企業) | 地方都市(病院) | |
|---|---|---|---|
| 地域 | 東京都杉並区 | 北海道札幌市 | 福岡県福津市 |
| 定員 | 10名(利用者10名) | 19人(利用者19人) | 50人(利用者48人) |
| 利用者内訳 | 0歳児5人、1歳児3人、2歳児1人、5歳児1人 | 0歳児0人、1歳児7人、2歳児12人 | 0歳児8人、1歳児16人、2歳児7人、3歳以上17人 |
| 開所時間 | 11時間(週7日未満) | 11時間+延長保育あり(週7日未満) | 11時間+延長保育+夜間保育あり(週7日開所) |
| 年間運営費 | 約2,400万円 | 約4,200万円 | 約6,000万円 |
| 年間運営費助成金 | 約1,900万円 | 約4,200万円 | 約5,500万円 |
運営費の助成金を有効活用すれば、採用や教育に注力できるので、安定的な保育所運営を実現できます。
企業主導型保育事業の整備費に対する助成金
企業主導型保育時事業では、施設の整備費に対しても助成金が出ます。
整備費に対する助成金は、「基本助成金(工事費+工事事務費)」と「加算金」の2つで構成されます。基本的に対象となる工事は、「創設(新築工事)」と「増築(増改築工事)」です。
基本助成金(工事費+工事事務費)

工事費とは保育所の工事(本体工事費)に対する助成金です。助成対象と認められた工事費の4分の3(75%)が交付されます。そして、工事事務費とは施工に関連する事務経費のことで、工事費の2.6%が上限です。
工事費は、保育所の規模と地域(都市部と都市部以外の標準)ごとに助成金単価の上限額が定められています。
| 定員数 | 都市部の助成金受給額の上限 | 標準(都市部以外)の助成金受給額の上限 |
|---|---|---|
| 20名以下 | 88,400千円 | 80,300千円 |
| 21~30名 | 92,700千円 | 84,200千円 |
| 31~40名 | 107,800千円 | 98,000千円 |
| 41~70名 | 122,900千円 | 111,700千円 |
| 71~100名 | 159,600千円 | 145,100千円 |
| 101名以上 | 192,000千円 | 174,000千円 |
出典:内閣府「企業主導型保育事業補助金実施要綱 単価表(令和3年5月12日【改定予定版】) 3.01 MB」
整備費の加算金
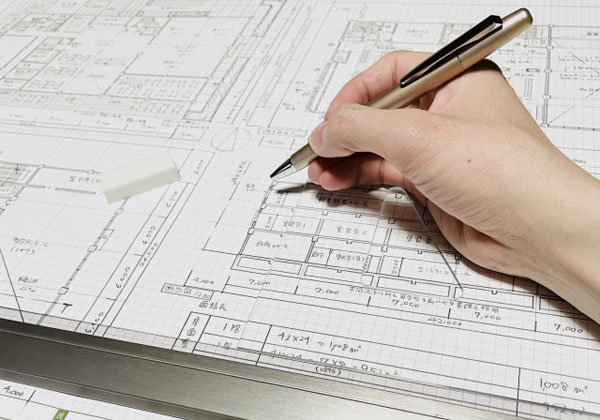
整備費の加算金とは、質の高い保育サービスを提供するために設けられている助成制度です。加算分には以下のような項目(一部抜粋)があります。
| 項目 | 内容 | 助成額目安 |
|---|---|---|
| 地域交流・一時預かりスペース加算 | 子育て支援用の地域交流スペース、または預かりサービス専用のスペースが対象 | 標準:2,630千円/都市部2,880千円(1事業当たり年額) |
| 病児保育スペース加算 | 病児保育に使う保育室または安静室などが対象 | 標準:20,970千円/都市部23,000千円(1事業当たり年額) |
| 環境改善加算 | 建物の入り口にスロープなど、児童の安全に配慮したものが対象 | 11,380千円(1事業当たり年額) |
| 設計料加算 | 工事にかかる設計料が対象 | 基本単価の5%が上限(1事業当たり年額) |
出典:内閣府「企業主導型保育事業補助金実施要綱 単価表(令和3年5月12日【改定予定版】) 3.01 MB」
整備費の助成事例
例えば、東京都特別区で定員20名の施設を新設し、地域交流事業や病児保育事業を実施すると、整備費に対する助成金の上限額は112,210千円前後です。実際は対象工事の実支出額の4分の3との比較によって助成額が決まります。
このように、助成金には様々な種類と条件があります。助成金に関連する最新情報や申請業務、行政の監査対応にお困りなら、スクルドアンドカンパニーにお声掛けください。助成金に精通したスタッフが対応させていただきます。
企業主導型保育事業の活用促進策で中小企業は助成金引き上げ
中小企業の積極的な保育事業への参入を後押しするため、企業主導型保育事業の活用促進策として、中小企業に対し助成金を引き上げる措置が講じられました。それによって、中小企業がより企業主導型保育事業を活用しやすくなっています。
- 施設運営費(年間)の企業自己負担分5%が3%に軽減されます。
例)年間運営費4,000万円の施設の場合、自己負担200万円→120万円に軽減 - 防犯・安全対策強化加算の単価を10万円→20万円/年に増額
- 共同利用・共同設置の連携費用に整備費100万円を加算
出典:内閣府「企業主導型保育事業補助金実施要綱 単価表(令和3年5月12日【改定予定版】) 3.01 MB」
企業主導型保育事業の助成金を受け取るまでの流れ
内閣府の「令和3年度企業主導型保育事業財務審査業務委託仕様書」を元に、企業主導型保育事業の助成金申請の流れについて解説します。
運営費、整備費の申請方法は若干異なります。ただ、申請先はどちらも公益財団法人「児童育成協会」です。助成決定後も各種申請を継続して行う必要があるため、必ず最新情報をチェックしましょう。
1.提出書類の用意・確認
企業主導型保育事業の申請に関連する書類は、110種類(運営費60種以上、整備費55種類以上)を超えます。助成金関連の書類は、専門家の証明や作成に時間を要するものが多いため、早い段階で着手する必要があります。
年々提出書類は増え続けており、中でも「保育内容」を追求するような書類の割合が増えています。
令和2年までは書類差戻し対応などありましたが、令和3年度からは提出書類に不備があった場合、審査対象とならない可能性があるので注意が必要です。令和3年度の募集はすでに終了しています。
2.1次審査
1次審査では、以下の項目がチェックされます。
| 財務適格性 | 決算報告書に関連する公認会計士等の書類や、預貯金の残高証明書の確認 |
|---|---|
| 社会保険料及び税金の納付実績 | 社会保険料の納入証明書と、未納がないことを証明する書類の確認 |
| 事業実績の審査 | 保育事業者型事業を実施する新規申請者は「施設等の5年以上の運営実績」と「4分の3以上の保育士割合(利用定員 20 人以上)」、保育施設の運営を委託する新規申請者は「委託事業者に対し、施設等の5年以上の運営実績」を確認する。 |
3.2次審査
2次審査では、以下の項目がチェックされます。
| 定量評価 | 「施設の職員体制が適正か」「施設が設置基準に適合しているか」「財務諸表」「職場の子育て支援に対する取り組み」など、他の申請者と比較できる項目を審査する。 |
|---|---|
| 定性評価 | 「保育所保育指針に国の基準が反映されているか」「コンプライアンスの遵守」「資金計画書の整合性」など、他の申請者との比較や数値的な判断が難しい項目を審査する。 |
| ヒアリング | 「自社の定員枠や地域枠の妥当性」「自社の保育ニーズ」を中心に、事業内容に関連する項目をヒアリングする。対象は新規申請者だけではなく、運営委託先・共同利用の契約を締結した契約企業を含む。 |
| 現地調査 | 事業内容や申請内容を確認するため必要に応じて現地調査を行う。ただし、内示前に現地調査が行われるパターンは確認されていない。 |
4.内示・助成決定
2次審査の評価点数や児童育英協会の意見などをもとに、一定基準をクリアした企業のみ「内示」という形で通知が届きます。
内示通知後に、児童育英協会からの差し戻しに対し全て対応すると、このタイミングで整備費助成金(工事費の4分の3)が確定します。
内示に向けて注意したいポイント
令和2年度より、内示決定以前に行った工事は助成対象外となります。
そのため、内示決定後(令和3年9月以降)から開業予定日までに工事を完了させる計画性が求められます。
まとめ
企業主導型保育事業の手厚い助成制度を活用すれば、保育事業への参入ハードルは下がります。ただ、申請手続きはとても複雑であり、提出までに1年近く要する書類も存在します。
令和3年度の新規申し込みはすでに終了しておりますが、今後いつこのような制度が再開されるかわかりません。また、令和3年度に内示が出た企業は、引き続き申請業務を継続していく必要があります。
設置基準や申請書類の内容は、施行後の状況や法整備の影響により流動的です。審査は年々厳しくなっており、行政の監査時に違反が見つかれば、助成が取り消しになる可能性もあります。
スクルドアンドカンパニーは、企業主導型保育所の申請業務から開設までフルサポートします。設置基準や面倒な申請手続きに関するご相談にも無料でお答えしますので、お気軽にお問い合わせください。